
ボイラー技士とはどんな仕事?資格概要とボイラー整備士との違いも解説

ボイラー技士は、ボイラー(簡易ボイラー・小型ボイラー・小規模ボイラー除く)の取り扱いに必要な国家資格です。
ボイラーはビルや病院、工場などさまざまな施設で使われており、これらの管理にはボイラー技士の存在が欠かせません。
ボイラー技士は、手に職をつけて長く働きたい人に向いています。
そこでこの記事では、ボイラー技士の概要や資格取得の方法について解説します。
ボイラー技士の仕事に興味がある人は、ぜひ参考にしてください。
この記事のポイント
ボイラー技士とは

ボイラー技士とは、ボイラー(簡易ボイラー・小型ボイラー・小規模ボイラー除く)の取り扱い業務に必要な免許です。
厚生労働大臣が指定した指定試験機関(安全衛生技術試験協会)が実施する免許試験に合格すると、都道府県労働局長から免許が交付されます。
ボイラーは大きさなどに応じて規格が定められており、一定以上の規模を有するボイラーを扱えるのは、ボイラー技士の免許がある人に限られています。
ボイラー技士はボイラーを扱ううえで、避けては通れない免許といえるでしょう。
ボイラー技士免許の種類
ボイラー技士免許は、二級・一級・特級の3種類です。級の区分に関係なく、全てのボイラーを取り扱うことができます。
ただし作業の指揮・管理を行うボイラー取扱作業主任者になるには、ボイラーの規模により必要な免許が異なります。
| 扱うボイラーの伝熱面積の合計 | ||
|---|---|---|
| 貫流ボイラー以外 | 貫流ボイラーのみ | |
| 特級ボイラー技士 | 500㎡以上 | |
| 一級ボイラー技士 | 25㎡以上500㎡未満 | 250㎡以上 |
| 二級ボイラー技士 | 25㎡未満 | 250㎡未満 |
ボイラーの免許にはボイラー技士の他にボイラー溶接士・ボイラー整備士があり、これらを総称して「ボイラー技士等免許」ということもあります。
ボイラー技士と整備士の違い

ボイラー整備士は、ボイラー技士と異なりボイラーの整備を行うために必要な免許です。
ボイラー整備士免許に等級はなく、ボイラー技士免許を保有している人は試験科目の一部が免除されます。一方でボイラー整備士免許があっても、ボイラー技士の試験科目の免除などはありません。
ボイラー関連の資格を取りたい人は、まずはボイラー技士から受験したほうがいいでしょう。
ボイラー技士・整備士の免許を取得すると、ボイラーの運転と整備を1人で担えるようになります。
ボイラー技士の仕事内容

ボイラー技士は、ビルや病院などの施設や建設現場で以下のような業務を行います。
・ボイラーの管理・点検
・ボイラー設置時の立ち会い
簡易ボイラーなど小規模なボイラーを設置している施設やボイラーのない施設を除いて、ボイラー技士なしでは施設の管理ができません。
ビルのメンテナンスなどの業務で、ボイラー技士の存在は欠かせないといえます。
建設現場でも、ボイラーを設置する箇所はボイラー技士が立ち会うことがあります。
このように、ボイラー技士はボイラーのある施設において欠かせない役割を果たしているといえるでしょう。
ボイラー技士に向いている人の特徴

ボイラー技士は単にボイラーを扱うだけでなく、作業の指揮・管理を行うボイラー取扱作業主任者になることもあります。
また、ボイラーは正しく取り扱わないと危険の伴う装置であり、火災や爆発を招くこともあります。
平均的なコミュニケーション能力があり、丁寧に作業できる人が向いているでしょう。
コミュニケーションが取れる
ボイラー技士は技術職ではありますが、ボイラー取扱作業主任者として作業の指揮・管理者の役割を担うこともあります。
仕事をするうえで、施設の管理者や作業者との円滑なコミュニケーションは欠かせません。
ボイラーは操作ミスにより事故が起きる可能性もあるため、適切なコミュニケーションを取って作業者との認識違いを防ぐことが大切です。
決して得意である必要はありませんが、最低限のコミュニケーションが取れる人が向いているでしょう。
ルールを守り細かいところまで丁寧に作業できる
ボイラーは些細なミス・異常から火災や爆発を招く可能性のある装置です。
ボイラー技士はボイラーを扱う有資格者として、ルールを守って丁寧に作業をすることが求められます。
液体の漏れや異音など、小さな異常も見逃すことなく作業ができる人が望ましいでしょう。
ボイラー技士になるメリット

ボイラー技士には、以下2つのメリットがあります。
・需要のある仕事で将来性が高い
・転職に強い
一定規模のボイラーはボイラー技士がいないと扱えないため、現場での需要は高いです。
需要のある仕事で将来性が高い
簡易ボイラー・小型ボイラー・小規模ボイラーを除き、ボイラーの取り扱いはボイラー技士が必要です。
ボイラーのある施設では、ボイラー技士がなければ施設の管理ができません。
一定規模のビルや病院、工場ではボイラーがないほうがめずらしいため、需要があり将来性が高いといえます。
ボイラー取扱作業主任者になれる範囲が広い一級・特級ボイラー技士になれば、現場からの需要もより高まるでしょう。
転職に強い
ボイラー技士は需要のある仕事であるため、転職にも強いです。
例えば、二級ボイラー技士はビルメンテナンスで役立つ4つの資格(ビルメン4点セット)に含まれています。
ボイラー技士を必要としない簡易ボイラーのビルメンテナンスでも、ボイラー技士の資格を持っている人を優遇する傾向があります。
実務経験を積んで一級・特級ボイラー技士になれば、さらに転職に強くなるでしょう。
ボイラー技士になるためには
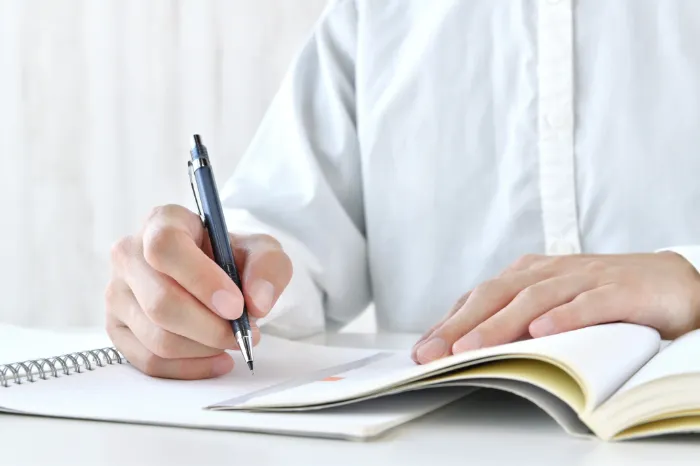
ボイラー技士になる方法として、主に以下の3つが挙げられます。
・大学・専門学校で学ぶ
・通信講座を受講する
・実技講習を受講する
二級ボイラー技士免許試験は誰でも受験できますが、免許を取得するには一定期間以上の実地修習または20時間のボイラー実技講習が必要です。
実務経験のない人がボイラー技士免許を取得する場合は、通信講座で勉強して実技講習を受講するのが最も現実的な方法でしょう。
大学・専門学校で学ぶ
大学や専門学校の機械工学科・設備工学などに進学すると、ボイラー技士の免許取得に必要な知識や技能を身につけられます。
企業とのつながりも深く、資格取得だけでなく就職時のサポートも見込めるでしょう。
ただし金銭的・時間的なコストが高いため、すでに大学を卒業した人には向かない方法です。
通信講座を受講する
できる限りお金をかけずに資格を取りたいなら、通信講座が有効です。
二級ボイラー技士の通信講座なら、3万円〜4万円程度の金額で受講できます。
自宅で簡単に学べるので、今の仕事を続けながら勉強できます。自分で計画を立てて勉強できる人なら、通信講座が向いているでしょう。
ただし、免許を取得するには実務経験または実技講習が必要になります。
実技講習を受講する
未経験者ができる限り早めにボイラー技士の免許を取得するなら、試験前に実技講習を受講しましょう。
試験そのものは実技講習なしでも受けられますが、免許取得には実技講習が必要です。
ボイラー実技講習は法令で定められた20時間講習のことで、例えば一般社団法人日本ボイラ協会では各都道府県の支部で定期的に実施しています。
実技講習を受けることで学習内容がよりイメージしやすくなり、知識の定着につながりやすいメリットもあります。


まとめ
ここまで記事を読んでくださりありがとうございます。
この記事を通じて、ボイラー技士について理解が深まりましたら何よりです。
ジャパンクリエイトは、製造業に特化した人材派遣会社としてさまざまな求人情報を掲載しておりますので、工場勤務に興味がある方はお気軽にご相談ください。